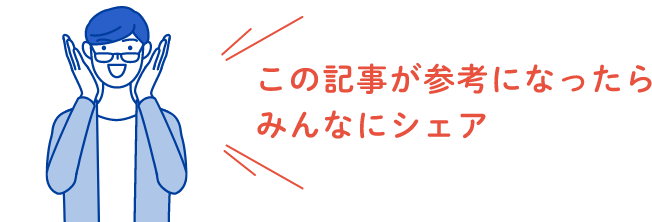高齢になると判断力や行動力が衰えるリスクが高まり、財産の管理や承継に関する重要な判断が難しくなることがあります。
また、遺言が無効になる、悪質業者による被害に遭うといったトラブルも起こりかねません。この記事では、そうした事態を未然に防ぐために活用できる「遺言」「生前贈与」「信託」「成年後見」といった各制度の概要と、それぞれの注意点をご紹介します。
大切な財産と家族を守るために、元気なうちからできる対策を一緒に考えてみませんか。
1.対策の必要性
年を重ねていくと、認知症を含む病気や投薬の影響で判断能力が低下する心配が日に日に強くなっていきます。判断能力が低下すると、財産について相続先・承継先を適切に決めることができなくなったり、遺言を遺したとして無効と判断されてしまうというリスクがあります。また、悪質な業者に騙されるなどして、財産を奪われてしまうリスクもあります。
また判断能力がそう衰えていなかったとしても、足腰を悪くして、あるいは怪我によって自由に動くことができなくなり、自ら出向いたり、資料を確認するなどして財産の管理を行うことが難しくなることもあります。
そのため、まだ判断能力・行動力があるうちに、自らの財産の承継先を決める、又は財産の管理処分を信頼できる方に尋ねる必要があります。
2.利用できる制度
判断能力・行動力の低下に備えた対策としては、以下の制度が活用できます。
遺言
遺言は、本人(遺言者)が亡くなったことを条件に生じる相続の内容を指定する行為で、書面(遺言書)を作成することによって行われます。
遺言を行う場合、遺言時に遺言をするに足る判断力(遺言能力)が必要であるとされており、これを欠いた時にされた遺言は無効とされてしまいます。仮にご本人として判断能力は「まだ大丈夫」と考えていたとしても、遺言の内容によっては、残された家族が怪しいと感じてしまうこともあります。
そのため、紛争の種を残さないためには、遺言はなるべく早めに作成をしておくことが肝心です。
詳しくは遺言書作成のページをご覧ください
生前贈与
遺言はご本人が亡くなったことを条件に効力が発生しますが、生前の段階で財産を家族・親族に承継させることも可能です。
もっとも、この場合、内容次第では相続の際に承継される財産の内容に影響を与えることがあります。また、生前贈与が行われると、相続人が複数いる場合、相続人間に不公平との感情が生まれ、紛争の種を残すことがあります。
そのため、贈与がされた時期、内容、条件(よくあるものとしては、自宅不動産を贈与された子は、親が亡くなるまでは不動産を処分してはならず、親を住まわせ続けるといった負担)を明確にしておくこと、遺言書を作成する場合は生前贈与がされている点について配慮した内容にするなど、対策が必要とされることもあります。
信託
信託は、特定の財産について、その財産から利益を受ける方(受益者)と信託の目的を決め、その目的に沿って管理・処分等を行うという制限を設けて、他の者に財産を譲渡等処分する行為です。
信託を活用することによって、例えば自宅不動産への居住、収益物件からの賃料収入といった利益を確保しつつ、これらの不動産の管理処分を、判断能力等の低下のリスクが少ない家族・親族等に委ねることが可能になります。
詳しくは信託のページをご覧ください
成年後見
成人は、本人や配偶者等の家族・親族らの申立てによって、裁判所に事理弁識能力を欠くと判断された場合、本人に代わって契約などを行ってもらう役割を負う者(成年後見人)を付ける審判を得ることができます。
成年後見人は、申立によって裁判所に選任をしてもらうことも可能ですが、判断能力が衰える前であれば、本人が自ら指名しておくことも可能です(任意後見)。
この成年後見人制度を利用することにより、判断能力を衰えたとしても、判断を第三者に代わって契約等の法律行為をしてもらうことができ、最初にご説明したようなリスクを軽減することができます。
まとめ
相続のツバサを運営する「翔栄法律事務所」は「相続問題」「入館問題」「労働問題」「行政規制」を中心に、幅広くお客様のお悩みに対応しております。相続に関するお悩みなどお気軽にご連絡ください。
- この記事の監修者
-

翔栄法律事務所
弁護士 岡本翔太
東京弁護士会所属(登録番号:52556)
- SNSで記事をシェアする
-