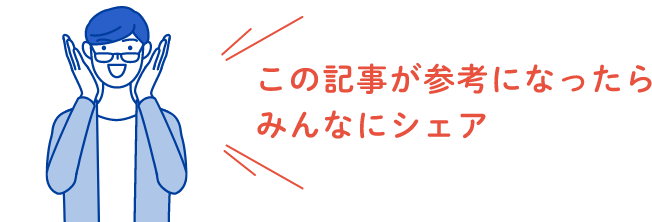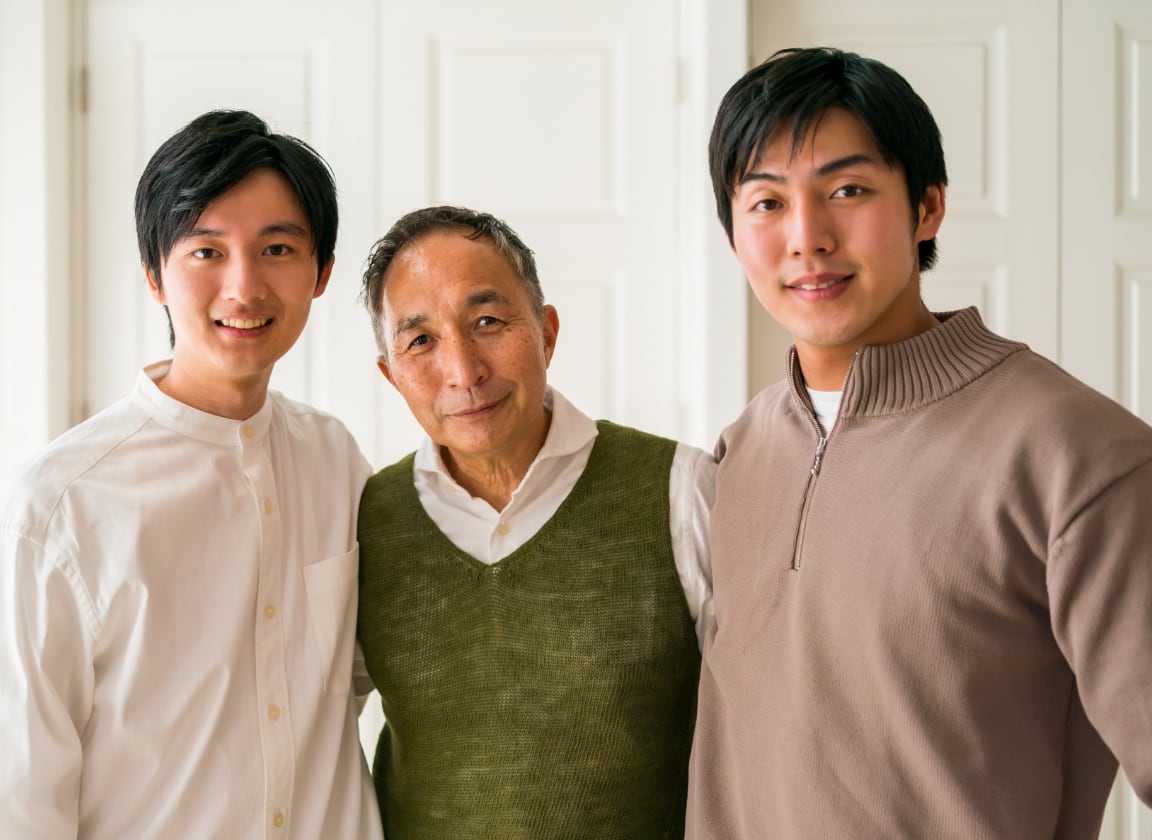
残された家族の将来が心配な方へ
生活や財産管理に不安があるご親族のために。
このページでは、ご自身が亡くなった後、遺産を受け取るご家族の生活や財産管理に不安がある方に向けて、弁護士が提案する相続の工夫や支援制度についてご説明しています。以下のような状況に心当たりのある方は、ぜひご相談ください。
- 子どもが障害を抱えていたり、年齢が幼く将来の管理が不安
- 配偶者が高齢であったり、資産管理の知識が乏しく、一人での対応が難しそう
このような場合には、遺言や信託などを活用し、ご自身の意思を反映させた形で、確実に遺産を管理・活用できる仕組みを整えておくことが大切です。将来に備えて、今できる準備を一緒に考えてみませんか。
1.対策の必要性
高齢になった場合はもちろん、そうでないとしても、もしも自身に予期せぬ事態が起きたらと考える人も多いかと思います。 その場合、幼い子ども、障害を抱えた子どもがいたり、又は高齢で判断力に不安のある親族が残されることへの不安がある方もいらっしゃると思います。
何も対策を講じていないと、ご本人が亡くなると、財産は法定相続分に従って相続され、相続人が複数いる場合は遺産分割協議が終わるまで処分をすることが難しくなります。
そのため、何かが起きる前に、財産の承継先、承継の条件、財産の管理者を決めておくなどして、残された家族が財産を適切に管理し、その財産を活用して生活ができるように備えておく必要があります。
2.利用できる制度
このような残された家族の判断能力・行動力に不安がある場合の対策として活用できる制度としては、以下のようなものがあります。
遺言
遺言は、本人(遺言者)が亡くなったことを条件に生じる相続の内容を指定する行為で、書面(遺言書)を作成することによって行われます。
遺言では、例えば、不動産や株式などの管理が難しいものは判断力ある親族に承継させ、預金などの管理が容易な財産を相続させる、又は判断力に心配な家族を居住させ続けることを条件にする不動産を承継させるなどの対策が可能です。 詳しくは遺言書作成のページをご覧ください。
生前贈与
遺言はご本人が亡くなったことを条件に効力が発生しますが、生前の段階で前述したような財産の承継を行うことも可能です。
もっとも、この場合、内容次第では相続の際に承継される財産の内容に影響を与えることがあります。また、生前贈与が行われると、相続人が複数いる場合、相続人間に不公平との感情が生まれ、紛争の種を残すことがあります。
そのため、贈与がされた時期、内容、条件(よくあるものとしては、自宅不動産を贈与された子は、親が亡くなるまでは不動産を処分してはならず、親を住まわせ続けるといった負担)を明確にしておくこと、遺言書を作成する場合は生前贈与がされている点について配慮した内容にするなど、対策が必要とされることもあります。
信託
信託は、特定の財産について、その財産から利益を受ける方(受益者)と信託の目的を決め、その目的に沿って管理・処分等を行うという制限を設けて、他の者に財産を譲渡等処分する行為です。
信託を活用することによって、例えば、判断能力等に不安がある家族に、自宅不動産の使用居住権や収益物件の賃料等の利益の一部を受益する権利を確保させつつ、管理処分は判断力を有する家族親族に委ねるといったことも可能になります。 詳しくは信託のページをご覧ください。
まとめ
相続のツバサを運営する「翔栄法律事務所」は「相続問題」「入館問題」「労働問題」「行政規制」を中心に、幅広くお客様のお悩みに対応しております。相続に関するお悩みなどお気軽にご連絡ください。
- この記事の監修者
-

翔栄法律事務所
弁護士 岡本翔太
東京弁護士会所属(登録番号:52556)
- SNSで記事をシェアする
-