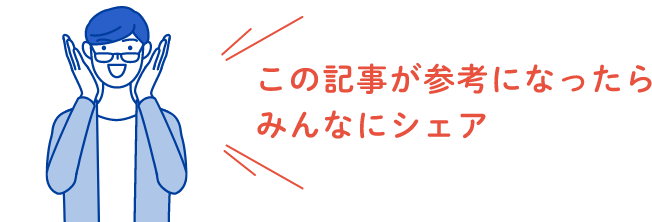遺言がない、遺言があっても内容が曖昧という問題で遺産の分け方でもめている方へ
このページでは、遺産の分割をめぐって相続人の間で争いが起きているケースについて、弁護士がどのようにサポートできるのかをご説明しています。以下のようなお悩みがある方は、ぜひご覧ください。
- 遺言がなく、遺産の分割方法でもめている
- 遺言はあるが、財産の分割方法が曖昧だったり、一部しか指定されておらず、もめている
- 遺産に評価額に争いのある不動産などの価値の高い物が含まれていて、公平な分割方法が分からない
相続財産をどう分けるかについて意見が食い違うと、親族間での関係悪化や長期的なトラブルにつながることがあります。弁護士にご相談いただくことで、法的な観点からのアドバイスや調停・審判手続までを一貫してサポートし、納得のいく解決を目指します。
1. 遺産分割ってなに(遺産分割の基礎知識)?
民法では、それぞれの相続人がどの程度の財産を相続すべきかという割合(法定相続分)しか定めていません。 そのため、遺言で財産の相続方法が具体的に指定されていない場合、個々の遺産を引き継ぐ相続人が確定していないため、不動産や株式の名義を特定の相続人に変更するなど、個々の遺産を相続人に承継する手続をとることができなくなることがあります。
そこで、このような場合には、不動産、動産、債権といった個々の財産を具体的にどのように配分するか、相続人間で協議して分割方法を決めたり(遺産分割協議)、裁判所に判断を仰いで分割方法を決定してもらうこと(遺産分割調停・審判)が必要になります。
(1) 分割をするにはどうしたらいい?(分割の手続)
①話し合い(遺産分割協議)
遺産分割は必ず裁判所を通さなければいけないものではありません。 当事者である相続人の話し合いで解決することも可能です。
話し合いにより条件が一致した場合、その内容を合意書(遺産分割協議書)にすることで、名義変更などの多くの手続を進めることができるようになります。
②遺産分割調停
協議が整わない、又は協議ができないときは、調停を申し立てることが考えられます。
調停では、裁判官と有識者から選ばれた調停委員2名が、当事者の言い分を聞いて、妥当と考えられる調停案を提示してくれることが通常です。 また、不動産や株式などの評価額がわかりにくい遺産がある場合には、裁判所が選任した不動産鑑定士や公認会計士を通じて、価値を鑑定してもらうこともできます。
もっとも、調停は、調停委員が相当な調停案を示すことはあっても、これに従うよう命令することはできません。
③遺産分割審判
調停を通じても、当事者で条件が一致しない、合意できない場合には、裁判所に命令(審判)を求めることになります。
審判に不服がある場合、当事者は2週間以内に異議(即時抗告)を申し立てて、別の裁判官に改めて審判をするよう求めることができます。 仮に即時抗告を申し立てなかった場合、審判は確定し、当事者は基本的にその内容を争うことはできなくなります。
(2) どうやって分割するの?(分割の仕方)
遺産が現預金であれば、その合計金額を法定相続割合に従って分ける方法が考えられます。
もっとも、例えば遺産の中に不動産が含まれている場合、特定の相続人に相続をさせてしまうと分配に偏りができてしまいます。 かといって、法定相続割合に基づいて共有にすると不動産が処分しづらくなってしまい、かえって相続人全員にとって不利益になることも考えられます。
そのため、分割方法としては以下のような種類のものがあり、調停・審判では、裁判所は「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」、どのように分割するかを調整します(民法906条)。
- 個々の財産の性質や形状を変更することなく分割する方法(現物分割)
- 一部の相続人に法定相続分を超える財産を取得させて、代わりに他の相続人に対する債務を負担させる方法(代償分割)
- 遺産を換価処分して、その代金を分配する方法(換価分割)
- 遺産の一部又は全部を具体的相続分による共有物件法上の共有取得とする方法(共有分割)
2. 弁護士に相談・依頼するメリットは?
自身で考えている案・交渉相手からの提案が持つリスクを分析してもらえる
遺産に多様な財産(不動産、動産、株式)が含まれていたり、複数の債務が含まれている場合、分割方法には様々なものがありえます。 その案が公平なものであるか、一見してわからないこともあります。さらには、仮に相続人同士で合意した分割内容であっても、債権者などの第三者に主張できないものも存在します。
そのため、交渉相手の提案した分割案はもとより、自身が考えた分割案ですらも、合意後に予期していないようなトラブルを招く事態になることもあります。
依頼をいただければ、交渉相手からの分割案も、ご自身が考えている分割案も、依頼者の方への不利益・リスクを分析、ご説明して、有利な解決を実現できるようにいたします。
相手方の態度次第では、調停・訴訟も選択肢にできる
相手方が頑として譲らないなど、交渉が煮詰まってしまった場合、妥当な解決を目指すためには、調停等で裁判所から意見をいただいたり、審判の形で従うべき分割方法を命令してもらうしかありません。
また、相手方が調停を起こした場合、望まなくてもこれに対応しなくてはなりません。 調停・審判は、法律に沿って言い分を整理した書面を提出したり、調停・審判の場で裁判官に説明を行うことで進行しますが、これは専門家の助力を得ることなく自分ですることは大変です。
依頼をいただければ、主張に関する書面の作成・提出、調停へ出廷して裁判官と議論を交わすことは、弁護士に任せていただけます。
相手方と直接話さなくてよくなる
遺産分割を話し合う場合、交渉相手は親族であったり、その親族が依頼した弁護士であるのが通常です。 親族に厳しいことを言わなければならないストレス、専門家である弁護士を相手取って交渉を行うストレスというのは、大変に感じる方も多いと思います。
依頼をいただければ、基本的に、相手方である親族やその弁護士への連絡は弁護士がすべて行いますので、直接話すことによるストレスから解放されます。
3. 弁護士費用
遺産分割の交渉等
着手金(交渉): 無料(税込)
着手金(+調停・審判): 無料(税込)
報酬金: 解決額の17.6%(税込)+最低保証額(下記参照)
※最低保証額は、交渉:33万円、調停:33万円です(調停が長引いても、追加費用は頂戴しません)。
※契約時に着手金を55万円お支払いいただく場合、交渉、調停・審判のいずれの段階での解決の場合でも、報酬金の算定から最低保証額は除外いたします。
遺産分割協議書作成(相続人調査、財産調査込み)
作成料: 110,000円~220,000円(税込)
※相続人間に対立がない場合に限ります。日本弁護士連合会職務基本規定に従い、対立があるケースではお引き受けできません。
※対立が生じた場合は辞任をさせていただきます。この場合、進行度合いに応じて、一部の費用を返還いたします。
4. ご相談から解決までの流れ(分割方針に対立がある場合の一例)
step1 相談
相談をより良いものにするため、お持ちであれば、以下のようなものを持参するようお願いしています。
- (遺言書が存在する場合)遺言書のコピー
- 親族から相続に関して受け取った書類
- 相続財産の内容がわかる書類(相談者が作成したメモでも結構です)
事案の内容や希望する解決内容をお聞きし、現時点の見通しと考えられる方針をご説明します。
お見積りをお示しします(ご提示が後日になることもあります)
step2 ご契約
- 相談時にご説明した見通しや方針にご納得して契約を希望される場合、契約書を取り交わします(相談時にお決めにならない場合には、郵送いたします)。
- 相談時に契約書を作成する場合、その場で読み上げ、ご説明をいたします。
- 郵送対応の場合、契約についてご不明点があれば、契約書作成前に電話等で回答をいたします。
※契約の際、身分証明書のコピーをとらせてていただきます。
step3-1 通知書の送付
step1で確定した方針に基づいて、相手方には書面を送付します。
書面には、例えば請求者の場合、以下のような事項を記載します。
- 弁護士が就任したこと、弁護士が以後の連絡窓口になること
- (遺産内容が不明な場合)遺産調査に必要な資料の開示依頼
- (相続人調査が未了の場合)相続人調査予定であること
- (分割案を決められる場合)分割案の提案
[送付する通知書面の一例]
step3-2 相続人調査・遺産調査など
相続人調査が未了である場合、遺産の調査が未了である場合、通知書の送付と並行して、又はその前にこれらの調査を開始します。
step4 交渉
- (分割方針が未確定である場合)調査した遺産の内容に基づいて、依頼者と調整させていただいた分割方針を確定します。
- 確定した方針に則って、分割案を相手方に連絡します。
- 交渉相手からすでに提案を受けている場合、その提案に対する回答(応じられる点があれば、その旨も)をします。
- 一致点を少しずつ増やしていき、合意ができないかを探ります。
★この場合で、条件が合致した場合、遺産分割協議書を作成することになります。
[遺産分割協議書の一例]
step5 調停
- 遺産調査に必要な資料を相手方が開示せず、話し合いを進められない場合、裁判所に開示を促してもらい、それでも応じない場合は資料や情報を持つ第三者に裁判所を通じた照会を行います。
- 不動産などの価値に争いがある場合、裁判所の選任した鑑定人に鑑定をしていただくこともあります。
- 合意に達した場合、調停により合意を行います。
- 合意に達しない場合、審判へ手続を進めます。
まとめ
相続のツバサを運営する「翔栄法律事務所」は「相続問題」「入館問題」「労働問題」「行政規制」を中心に、幅広くお客様のお悩みに対応しております。相続に関するお悩みなどお気軽にご連絡ください。
- この記事の監修者
-

翔栄法律事務所
弁護士 岡本翔太
東京弁護士会所属(登録番号:52556)
- SNSで記事をシェアする
-