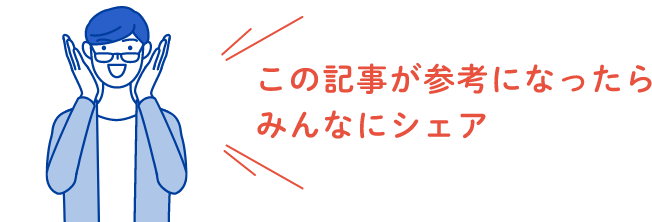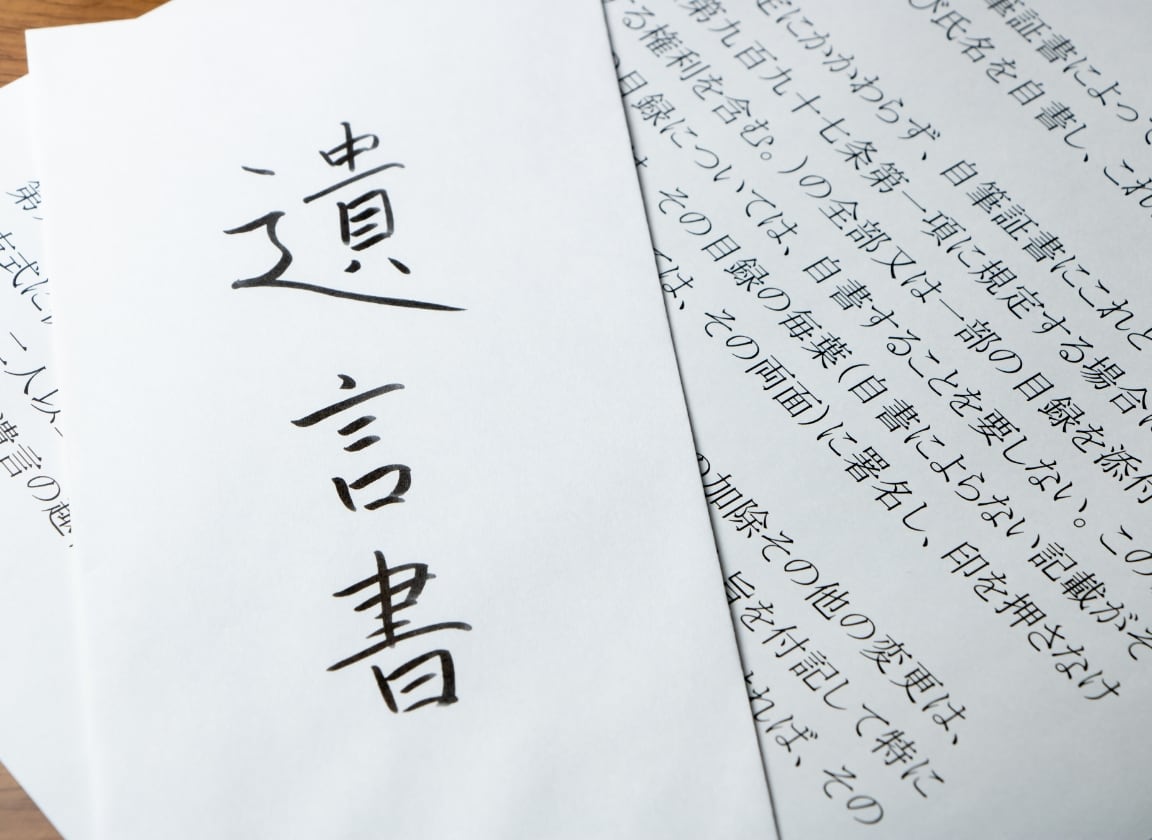
その遺言、本当に有効ですか?
判断能力が疑われる遺言や、内容・形式に不安がある方へ
このページでは、遺言が有効かどうかに不安がある方に向けて、弁護士によるサポート内容を詳しく解説しています。以下のようなお悩みがある場合は、ぜひご覧ください。
- 認知症、投薬、病気などで遺言者の判断力が怪しい時期に遺言書が作られている
- 遺言が自筆で書かれたもので、内容から見ても怪しい
遺言の有効性が疑われる場合でも、弁護士が証拠の収集から交渉・裁判まで一貫して対応します。相続トラブルを防ぐために、早めのご相談をおすすめします。
1. 遺言の効力についての基礎知識
遺言は遺言者の死後になって初めて効力が生じます。遺言の内容、遺言が存在すること自体が死後初めて明らかになることも珍しくありません。 そのため、遺言は、本物か、あるいは遺言者の真意に沿ったものであるか(誰かに書かされたものでないか)といった理由からして、遺言の効力が問題にされることがあります。
遺言の効力が問題になるケースとしては、主に以下のようなものがあります。
(1) 遺言能力がない
遺言能力とは、遺言をするための能力です。 遺言が残されていたとしても、遺言の作成時に遺言能力を欠いている場合、遺言は無効と扱われます(民法963条)。
そこで遺言能力の有無の基準が重要になりますが、法律には、満15歳に達していること(民法962条)以外に明確な基準を定めていません。 判断能力が低下しているような状態、例えば認知症、投薬、病気などの事情がある場合、遺言能力の有無が問題とされることが多くなります。
もっとも、遺言能力の有無は、例えば長谷川式認知症スケール(認知症のテスト)の点数が一定以下であれば無効である、あるいはこの薬を一定量以上投薬していれば無効になるといった、画一的基準がある、機械的に判断できるというものではありません。 遺言当時の一切の事情を総合的にみて判断が行われています。
(2) 形式を守っていない
遺言は、法律にどのようなことを書かなければならないか、どのように作らなければならないかといった形式が決められていて、その形式を守らないと無効になります(要式行為)。
守らなければならない形式としては、自筆証書遺言の場合、以下のようなものがあります。
- 全文(添付された相続財産の目録部分を除く)、日付、氏名を自書する
- 押印を行う
- (変更がある場合)遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印を行う
過去、録音で残された遺言、印鑑の代わりに花押が用いられた遺言などが無効とされています。
(3) 遺言が偽造された
遺言は遺言者の死後に存在が明らかになることもあります。 しかし、その時には遺言者はすでに亡くなっているため、本物か否かを尋ねることはできません。
そのため、公証人立合いの下で作成された公正証書遺言や秘密証書遺言のような偽造を防止する措置が講じられていない場合、経緯や内容によっては偽造されたものではないかという疑念が生じ、真偽が争われることがあります。
遺言が偽造されたものである場合、正確に言えば、そもそも遺言者の遺言は存在しないため、(存在した遺言が)無効になるというのではなく、そもそも遺言は存在しなかったということになります。
2. 弁護士に相談・依頼するメリットは?
どういった証拠を集めればよいかがわかる
満15歳に達したときに作成されたという点以外に、遺言能力の判断に決まった基準はありません。 そのため、遺言の有効性を争う場合、どういった事実関係を主張し、どういった証拠を集めて提出すべきかは、ケースごとに判断をしなければなりません。
依頼をいただければ、専門家として、過去の事例や経験にもとづいて、そのケースではどういった事情を伝えるべきか、どういった証拠があるかを考え、集めて、紛争に有利になるように進めます。
無効が認められなかった場合に備えて効率的に動くことができる
特定の相続人を相続から廃除したり、相続分を極端に減らす遺言の場合、遺言の無効の主張が認められないとしても、遺留分侵害額の請求を行うことが考えられます。
しかし、遺留分侵害額請求は1年で時効が成立し、請求ができなくなってしまいます。 そのため、遺言無効と並行して動くことが通常ですが、計算方法やそのために必要な資料などは専門家以外にはなかなか難しい問題があります。
遺言無効確認が認められなかった場合に備えて、遺留分侵害額請求も併せてご依頼いただくことも可能です。
相手方と直接話さなくてよくなる
遺言無効確認請求の場合、その相手方は親族であったり、その親族が依頼した弁護士であるのが通常です。
親族に厳しいことを言わなければならないストレス、専門家である弁護士を相手取って交渉や裁判を行うストレスというのは、大変に感じる方も多いと思います。 依頼をいただければ、基本的に、相手方である親族やその弁護士への連絡は弁護士がすべて行いますので、直接話すことによるストレスから解放されます。
相手方の態度次第では、調停・訴訟も選択肢にできる
遺言の無効を主張する場合、交渉による解決が難しい場合が多く、調停等で裁判所を通じて説得をしてもらったり、訴訟を通じて有効性を確定する判決を取得せざるを得ないこともあります。
請求を受けた側は、望まなくても、相手方が調停や訴訟を起こしてきた場合、これに対応しなくてはなりません。
調停や訴訟は、法律に沿って言い分を整理した書面を提出したり、調停・訴訟の場で裁判官に説明を行うことで進行しますが、これは専門家の助力を得ることなく自分ですることは大変です。
依頼をいただければ、主張に関する書面の作成・提出、調停・訴訟へ出廷して裁判官と議論を交わすことは、弁護士に任せいただけます。
3.ご料金について
着手金:遺言無効により変動する取得額の8.8%(税込) ※最低着手金あり(※1、※2)
報酬金(勝訴+遺産分割事件を依頼いただく場合):遺産分割事件の着手・報酬が発生します※3
報酬金(勝訴+遺産分割事件を依頼されない場合):遺言無効により変動する取得額の17.6%(税込)
- 最低着手金は段階ごとに異なります(交渉:22万円、調停:44万円、訴訟:66万円)
- 契約時点では遺産評価額の算定ができない場合、最低着手金をお支払いいただいたうえ、評価額確定時に差額を追加着手金としてお支払いいただきます
- 遺産分割事件を途中解任される場合、「勝訴+遺産分割事件を依頼されない場合」の報酬金を頂戴します
4.ご相談から解決までの流れ(分割方針に対立がある場合の一例)
step1 相談
相談をより良いものにするため、お持ちであれば、以下のようなものを持参するようお願いしています。
- 遺言書のコピー
- 親族から相続に関して受け取った書類
- 遺言作成時の遺言者の健康状態がわかる資料(認知症のテスト結果など)
- 遺産の内容がわかる資料
事案の内容や希望する解決内容をお聞きし、現時点の見通しと考えられる方針をご説明します。
お見積りをお示しします(ご提示が後日になることもあります)
step2 ご契約
相談時にご説明した見通しや方針にご納得して契約を希望される場合、契約書を取り交わします(相談時にお決めにならない場合には、郵送いたします)。
相談時に契約書を作成する場合、その場で読み上げ、ご説明をいたします。
郵送対応の場合、契約についてご不明点があれば、契約書作成前に電話等で回答をいたします。
※契約の際、身分証明書のコピーをとらせていただきます。
step3-1 通知書の送付
step1でご了解いただいた方針に基づいて、相手方に書面を送付します。
書面には、例えば請求者の場合、以下のような事項を記載します。
- 弁護士が就任したこと、弁護士が以後の連絡窓口になること
- (遺言無効を主張する側である場合)遺言書作成時の遺言者の健康状態がわかる資料開示の依頼
step3-2 証拠収集など
相手方の協力がなくても証拠の取得が見込める場合(例えば、遺言者の医療記録など)、独自に証拠集めを進めます。
step4 交渉
遺言の無効を主張する側であれば無効であることの根拠を、有効と主張する側であれば有効とする根拠を通知します。
(通常は相手方の無効主張が先行しているため、その反論を主張することが多いでしょう)
調停・訴訟により紛争が長引く不利益や、無効・有効の主張の見通しなどから、依頼者の方として譲歩が可能であれば、譲歩による和解を探ります。
step5 裁判
- 基本的には訴訟より先に調停を申し立てます。
- 収集した証拠に基づいて、主張を組み立てて、書面を作成・提出します。
- 相手方が資料の開示に非協力的な場合、裁判所に開示を促してもらい、それでも応じない場合は資料や情報を持つ第三者に裁判所を通じた照会を行います。
- 合意に達した場合、調停又は裁判上の和解により合意を行います。
- 合意に達しない場合、訴訟へ手続を進め、判決を求めます。
step6 遺産分割の紛争へ
遺言が無効と判断された場合はもとより、遺言が有効と判断された場合も、遺産分割の問題が残されることがあり得ます。 この場合の進め方については、遺産分割紛争のページをご覧ください。
まとめ
相続のツバサを運営する「翔栄法律事務所」は「相続問題」「入館問題」「労働問題」「行政規制」を中心に、幅広くお客様のお悩みに対応しております。相続に関するお悩みなどお気軽にご連絡ください。
- この記事の監修者
-

翔栄法律事務所
弁護士 岡本翔太
東京弁護士会所属(登録番号:52556)
- SNSで記事をシェアする
-