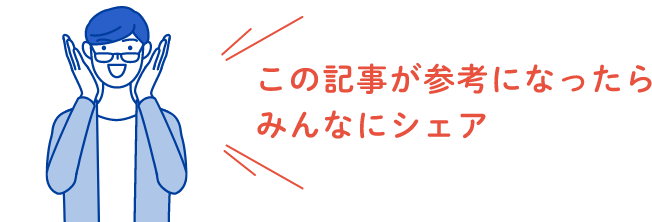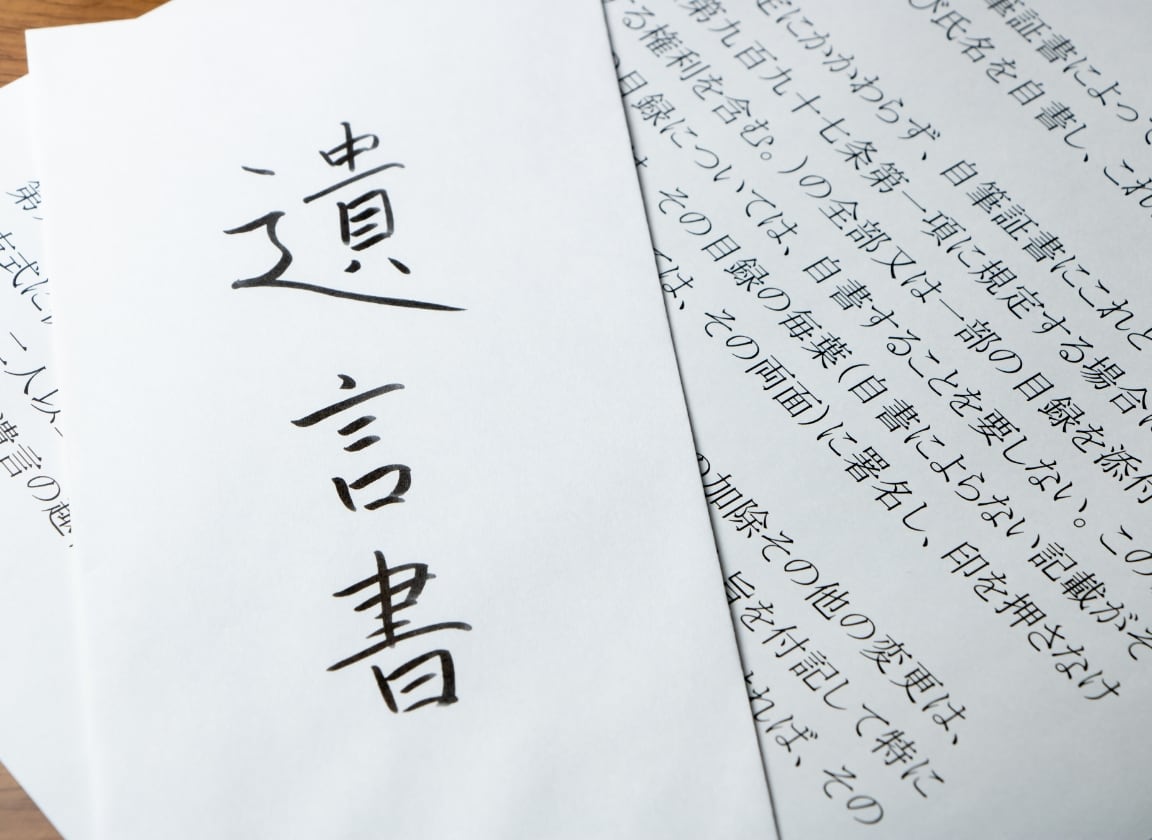遺言の内容に不安がある方へ。
複雑な財産や信託にも対応した、安心できる遺言の作成をサポートします。
このページでは、遺言に関する以下のお悩みについて、弁護士によるサポート内容をわかりやすくご説明しています。
- 財産に株式や収益物件があって、遺言の内容が複雑になりそう
- 遺言の内容に問題がないか、無効にならないか不安
- 遺言で信託を設定したい
- 死後、遺言どおりに分配がされるか不安がある
株式や収益物件などをお持ちの方や、遺言の有効性に不安のある方も、安心してご相談ください。信託を活用した遺言の作成や、確実な遺言執行まで、弁護士がしっかりと対応いたします。
1. 遺言の基礎知識
遺言は、一般的には「ゆいごん」と読まれていますが、法律用語としては「いごん」の呼称が使用されています。
遺言は、遺言者の死を条件として生じる相続の効果(内容)を遺言者によって決めることができる手段です。 遺言がない場合、相続財産(遺産)は法定相続人に法定相続分に従って分配(相続)されることになります。
そのため、遺言の有効性・内容は相続人にとっても重要な事項ではありますが、遺言の効力が問題とされるのは主に遺言者の死後になります。 この段階では、無効だから、内容が曖昧だからといってやり直すということはできません。 そこで、遺言は、無効にならないよう、また内容が曖昧にならないように作成する必要があります。
また、遺言の効果が生じるときには遺言者は亡くなっているため、遺言の内容を実現する業務(遺言執行業務)は、他者に任せざるを得ません。 そこで、遺言では、このような業務を担うもの(遺言執行者)を指定することも可能です。
(1) 遺言にはどのようなやり方があるの?(遺言の方式)
遺言の作成方法としては、以下の3つがあります。
- 自筆証書遺言:自筆
- 公正証書遺言:公証人の下で作成する方式で行う
- 秘密証書遺言
(2) 遺言はどういった場合に無効になるの?
遺言は、作成時点の遺言者が遺言を行うことができる能力(遺言能力)を備えてなければならず、遺言能力を欠いた状態でされた遺言は無効とされます。 また、遺言を行う場合、法律が定める形式(⑴で述べた遺言の方式ごとにルールが違います)に沿って行わなければならず、形式を守らない場合も遺言は無効とされてしまいます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
(3) 遺言の限界
遺産の承継先を決める遺言ですが、その効果にも限界があります。
特定の相続人を相続から排除する場合、法律で相続人に認められた最低限の保障分(遺留分)を下回るような内容は、相続人が下回った部分の支払いを求めた場合、制限を受けます(遺留分侵害額請求)。
また、例えば、財産を一人の相続人に集中して相続させ、債務を他の相続人に相続させるような遺言は、本来であれば財産に差押えなどができた債権者を害することになるため、債権者との関係では制限されます(民法902条の2)。
その他、遺産を承継した者が死亡した場合の次の承継先を遺言で指定すること(後継ぎ遺贈)も認められていません。 (ただし、こちらは、同様の効果を家族信託によって実現することが可能とされています。)
2. 弁護士に依頼するメリット
遺言に関しては、司法書士など他の専門家もお取り扱いがありますが、その中から弁護士に依頼するメリットをご説明します。
争いにならない内容を残したい場合に安心
遺言は遺言者が相続の内容を決定することで、相続間で紛争が生じることを防ぐメリットがあります。 このような紛争防止のメリットを実現するには、遺言は内容に曖昧さや法律上認められない内容を残さないように作成しなければなりません。
法律の専門家の中で、唯一弁護士のみが、家事調停を含めたすべての裁判手続の代理人になることができ、どういった内容の遺言が紛争を招くか、経験や過去の裁判例から熟知しています。 そのため、遺言の中に争いにならない内容を残さないようにしたい場合に安心です。
遺言執行業務に裁判が含まれても安心して任せることができる
遺言執行業務をする過程で、債権者や一部の相続人などが遺言の効力を巡って遺言執行者に対して裁判手続を起こすことがあります。 この場合、遺言執行者が裁判の当事者になる場合があります。
弁護士が遺言執行者に選任されていれば、訴訟のプロとして自らその裁判を進めることができます。 そのため、遺言者の方としては、遺言作成から遺言執行業務までの全体を見届ける役割を安心して任せることができます。
3. ご料金
遺言書作成(信託なし):220,000円~550,000円
遺言書作成(信託あり):信託財産評価額の1.1%+220,000円
遺言執行者への就任:相続財産額の2.2%+264,000円(最低報酬330,000円)
- 税理士関与の下で相続税対策を施した遺言内容を組成する場合、別途税理士費用を実費として頂戴します。
- 遺言執行業務の報酬は、相続財産の額が3000万円を超える場合、減額をいたします。
- 遺言執行業務として裁判手続きを行う場合、費用を別途頂戴します。
4. ご相談から解決までの流れ(分割方針に対立がある場合の一例)
step1 相談
- 相談をより良いものにするため、お持ちであれば、以下のご準備をお願いします。
・お持ちの財産について、メモを作成するなどして、ご説明できるよう整理をお願いします。
・どの親族にどの財産を残すか、ご希望を説明できるよう整理をお願いします。 - お見積りをお示しします(ご提示が後日になることもあります)。
- お身体が悪い場合など、事務所にいらっしゃることが難しい方の場合、ご自宅や介護施設などに訪問して相談をうかがうことも可能です。
※場所によっては交通費や相談料を別途頂戴することがあります。
step2 ご契約
- 相談時にご説明した進行にご納得して契約を希望される場合、契約書を取り交わします(相談時にお決めにならない場合には、郵送いたします)。
- 相談時に契約書を作成する場合、その場で読み上げ、ご説明をいたします。
- 郵送対応の場合、契約についてご不明点があれば、契約書作成前に電話等で回答をいたします。
- ※契約の際、身分証明書のコピーをとらせていただきます。
step3 打合せ(遺言書案のすり合わせ含む)
- 遺産の内容などに曖昧な点がある場合(例えば、お持ちの預金口座の情報に不足がある場合)、ご本人や親族に資料集めを依頼します。
- 遺言者のご希望や、財産の調査結果を踏まえて、遺言書の内容案を作成いたします。こちらを依頼者の方に確認していただき、ご意思を実現できるように修正を重ねていきます。
step4 遺言書の作成
- 公正証書遺言の方式によって作成をいたします。
- 通常は公証役場で作成をしますが、公証役場に追加費用を支払えば、ご自宅や介護施設などの公証役場外での作成も可能です。
step5 遺言執行業務(ご依頼の場合)
遺言者が亡くなられた場合、遺言執行者として、以下のような遺言執行業務を行います。
- 預金口座の解約と分配
- 不動産や株式などの登記・登録の名義変更への協力
- 遺言無効確認請求等の調停・訴訟の対応
まとめ
相続のツバサを運営する「翔栄法律事務所」は「相続問題」「入館問題」「労働問題」「行政規制」を中心に、幅広くお客様のお悩みに対応しております。相続に関するお悩みなどお気軽にご連絡ください。
- この記事の監修者
-

翔栄法律事務所
弁護士 岡本翔太
東京弁護士会所属(登録番号:52556)
- SNSで記事をシェアする
-