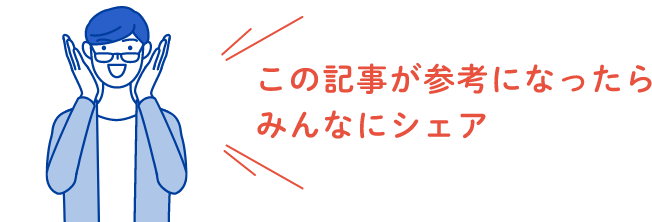- ある日、親族の依頼した弁護士から「遺留分」を請求する通知を受けとった
- 相続人だったが、遺言で自分の相続分を減らされてしまった、全くなくなってしまった方
- 遺留分を請求したいが、計算方法や進め方が分からない
1. 「遺留分」ってなに?(遺留分の基礎知識)
遺留分とは、民法で定められた、相続が起きた場合に、亡くなった方の意思(遺言)でも排除ができない相続人の最低限の取り分のことです。 遺族である相続人への生活保障、遺産形成に貢献したことへの清算、相続人間の公平性の確保などが目的・役割であるとされています。
※遺言がない場合、通常は「遺留分」の請求ではなく、「法定相続分」をベースとした遺産分割を求めるのが通常です。詳しくは、こちらをご覧ください。
遺留分侵害額の請求は、早ければ、被相続人が亡くなって1年程度で請求できなくなることがあります。
(1) 遺留分ってどれくらい?(計算方法)
遺留分は、
- 直系尊属のみが法定相続人である場合は法定相続分の3分の1
- それ以外の場合は2分の1
他の相続人に対して請求をする場合、この遺留分のうち、遺言等によって侵害された(減らされてしまった)部分に相当する額(遺留分侵害額)を請求することになります。
この遺留分侵害額は、遺留分の額から、以下を調整して算出されます:
- 遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額を差し引く
- 遺産分割される財産がある場合は具体的相続分に相当する額を差し引く
- 遺留分権利者が承継した債務を加える
簡単に計算できるケースもありますが、贈与や遺贈、特別受益の有無や金額に争いがあったり、相続財産に不動産などの高額で評価が難しいものが含まれる場合など、前提から争いになるケースもあります。
そのため、交渉や調停などの裁判手続を通じて金額を確定する必要が生じることがあります。
(2) どうやって請求するの?
裁判所を必ずしも利用する必要はなく、当事者(相続人)同士で交渉し、和解して解決することも可能です。
交渉で和解ができない場合、原則として、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。 調停は、当事者間に合意がない限り、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てる必要があります(家事事件手続法245条1項)。
調停を前置しない例外的な事情がある場合や、調停が不成立となった場合には、訴訟を提起することになります。 訴訟では、相手方の住所地のほか、相続開始時の被相続人の住所地、または請求者の住所地の管轄裁判所に提起できます。
(3) いつまでに請求すればいいの?(時効の問題)
以下の場合には、遺留分侵害額請求権は時効により消滅し、請求ができなくなります(民法1048条)。
- 相続の開始(≒被相続人の死亡)および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内
- 相続開始の時から10年を経過した場合(知っていたか否かにかかわらず)
(4) いつ支払えばよいの?
遺留分は被相続人を保護するための制度なので、侵害を受けた遺留分権利者(またはその承継人)が遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが必要であり、請求がない段階では受遺者に支払義務は生じません。
もっとも、請求を受けた場合には、遺留分権利者が価額弁償請求権を確定的に取得し、かつ受遺者に対し弁償金の支払いを請求した翌日から年3%の遅延損害金が発生します(最高裁平成20年1月24日判決参照)。
そのため、遺留分侵害額を請求する書面を受け取った方は、早急に弁護士に相談するなどの対応をとられた方が安全です。
2. 弁護士に相談・依頼するメリットは?
複雑な遺留分の計算を任せられる
請求する側でも、される側でも、まずは自分にとって妥当と考えられる遺留分額が交渉のベースになります。 資料を精査して、具体的な遺留分を算定します。
遺留分計算に必要な資料の当たりを付けられる
遺留分の算定には、相続財産の内容などを確認するための資料が不可欠です。 しかし、算定に必要な資料は事案によって異なり、どういったものを探せばよいか、相手方や第三者にどういったものの開示を依頼すればよいか、経験がないとわかりません。 事案をお聞きして、収集すべき資料の内容や収集方法をご提案します。
相手方と直接話さなくてよくなる
遺留分侵害額請求の場合、交渉相手は親族であったり、その親族が依頼した弁護士であるのが通常です。 親族に厳しいことを言わなければならないストレス、専門家である弁護士を相手取って交渉を行うストレスというのは、大変に感じる方も多いと思います。
依頼をいただければ、基本的に、相手方である親族やその弁護士への連絡は弁護士がすべて行いますので、直接話すことによるストレスから解放されます。
相手方の態度次第では、調停・訴訟も選択肢にできる
請求者側の場合、相手方が資料開示に応じなかったり、不当に少ない額しか支払わないとの態度だと、妥当な解決を目指すためには、調停等で裁判所を通じて説得をしてもらう、訴訟を通じて支払いを命令する判決を取得するしかありません。
請求を受けた側は、望まなくても、相手方が調停や訴訟を起こした場合、これに対応しなくてはなりません。 調停や訴訟は、法律に沿って言い分を整理した書面を提出したり、調停・訴訟の場で裁判官に説明を行うことで進行しますが、これは専門家の助力を得ることなく自分ですることは大変です。
依頼をいただければ、主張に関する書面の作成・提出、調停・訴訟へ出廷して裁判官と議論を交わすことは、弁護士に任せていただけます。
遺言無効と主張されているケース
遺留分は、通常、遺言によって相続人の相続財産が減らされている・ゼロにされている場合に、これを相続人が不満に思って主張されるのが一般です。
そして、遺言の内容について不満に思う相続人は、まずは遺言の効力を争えないかと考えることが多く、遺留分の請求は、遺言無効の主張が認められない場合の予備的なものとして行うケースが多々あります。
したがって、次のような状況がよくあります:
- 遺留分自体は、相続人の立場によって自動的に決まるため、通常は権利の有無や割合を争うことはできません(欠格事由がない限り)。
- ただし、遺留分の金額は問題になることがあります。たとえば、不動産の価格や、基準となる相続財産の額が贈与などで流出している場合などです。
3.ご料金
(1) 遺留分侵害額の請求をする場合(請求をする側)
着手金(交渉): 無料(税込)
着手金(+調停): 無料(税込)
着手金(+訴訟): 無料(税込)
報酬金: 解決額の17.6%(税込)+最低保証額(下記参照)
※最低保証額は、交渉:22万円、調停:22万円、訴訟:22万円です。
※契約時に着手金を55万円お支払いいただく場合、交渉、調停、訴訟のいずれの段階での解決の場合でも、報酬金の算定から最低保証額は除外いたします。
※申立て・請求内容に、遺言無効などの他のものを含める場合、別途費用を頂戴することがあります。
※訴訟は控訴審以降、別途費用を頂戴します。
(2) 遺留分侵害額の請求をされた場合(請求をされる側)
着手金(交渉): 22万円(税込)
着手金(+調停): 追加33万円(税込)
着手金(+訴訟): 追加22万円(税込)
報酬金:[請求額 − 解決額]の17.6%(税込)
※申立て・請求内容に、遺言無効などの他のものが含まれている場合、別途費用を頂戴することがあります。
※訴訟は控訴審以降、別途費用を頂戴します。
4.ご相談から解決までの流れ(一例)
step1 相談
相談をより良いものにするため、お持ちであれば、以下のようなものを持参するようお願いしています。
- 遺言書のコピー
- (請求を受けている方からの相談の場合)相手方から届いた書類
- 相続財産の内容がわかる書類(相談者が作成したメモでも結構です)
事案の内容や希望する解決内容をお聞きし、現時点の見通しと考えられる方針をご説明します。
お見積りをお示しします(ご提示が後日になることもあります)
step2 ご契約
相談時にご説明した見通しや方針にご納得して契約を希望される場合、契約書を取り交わします(相談時にお決めにならない場合には、郵送いたします)。
相談時に契約書を作成する場合、その場で読み上げ、ご説明をいたします。
郵送対応の場合、契約についてご不明点があれば、契約書作成前に電話等で回答をいたします。
※契約の際、身分証明書のコピーをとらせてていただきます。
step3 通知書の送付
step1で確定した方針に基づいて、相手方には書面を送付します。
書面には、例えば請求者の場合、以下のような事項を記載します。
- 弁護士が就任したこと、弁護士が以後の連絡窓口になること
- 遺留分侵害額を請求する旨(遅延損害金を発生させるために必要です)
- (算定が可能である場合には)請求額
- (算定が現時点で困難な場合には)算定に必要な資料の開示依頼
請求を行う場合、通常は、請求日に争いがないようにするため、配達証明付き内容証明郵便を使用して書面を送ります。
[送付する通知書面の一例]
step4 交渉
まずは(請求者側であれば)相手方や第三者から算定に必要な資料を収集し、(請求を受ける側であれば)相当な資料を開示して、お互いに妥当と考える金額を算定できるよう状況を整えます。
請求者側では、算定するに足る資料が揃った場合、請求額を通知します。
→ 相手方の非協力的態度などによって資料が揃わない場合は step5 へ
請求を受ける側では、依頼者と、妥当と考えられる金額等の条件を擦り合わせ、そのうえで相手方と条件交渉を図ります。
金額等の条件について合意に達しない場合、裁判へ手続を進めます。
★この場合で、金額に合致が見られる場合、和解をすることになります。
[和解書の一例]
step5 裁判
基本的には訴訟より先に調停を申し立てます。
請求者側で相手方が資料の開示に非協力的な場合、裁判所に開示を促してもらい、それでも応じない場合は資料や情報を持つ第三者に裁判所を通じた照会を行います。
不動産などの価値に争いがある場合、裁判所の選任した鑑定人に鑑定をしていただくこともあります(鑑定嘱託の申立て)。
合意に達した場合、調停又は裁判上の和解により合意を行います。
合意に達しない場合、訴訟へ手続を進め、判決を求めます。
まとめ
相続のツバサを運営する「翔栄法律事務所」は「相続問題」「入館問題」「労働問題」「行政規制」を中心に、幅広くお客様のお悩みに対応しております。相続に関するお悩みなどお気軽にご連絡ください。
- この記事の監修者
-

翔栄法律事務所
弁護士 岡本翔太
東京弁護士会所属(登録番号:52556)
- SNSで記事をシェアする
-